推荐信息:

秦の始皇帝は東海に蓬莱(ほうらい)・方丈(ほうじょう)・瀛洲(えいしゅう)という三神山があって仙人が住んでいるということを聞き、方士を不老不死の薬を探しに行かせた。最初に不老不死の薬を探す旅に立ったのは燕の国の人盧生であった。盧生は今の秦皇島から出発したが、たどり着くことができなかった。今でも、秦皇島市内の東山公園には「秦の始皇帝、不老不死の薬を求める出発地」と呼ばれる遺跡がある。1992年、ここに高さ6メートル、重さ80トンのみかげ石で作られた秦の始皇帝の彫像が立てられた。
盧生に次ぎ、徐福が始皇帝に派遣され、不老不死の薬を求める旅に立った。初回の旅では徐福は不老不死の薬を見つけることはできなかったが、帰国後始皇帝に「蓬莱の仙山に登って不老不死の薬を見つけたが、優れた男女と職人を連れて行かないと仙人が薬をくれない」と伝えた。秦の始皇帝は若い男女3000人のほか、優れた職人を選抜して、徐福と共に不老不死の薬を探す旅に行かせた。二回目の旅で、徐福はまたもや失敗したが、竜と鯨に阻まれてたどり着けなかったと始皇帝に報告した。三回目の旅に秦の始皇帝自らが参加したが、不老不死の薬がなおも見つけることはできなかった。結局、徐福は中国に戻らず、今の日本にたどり着き、富士山の麓で没したと言われている。
日本には、徐福に関わる伝説と記録が多く伝わっている。徐福が日本史上で有名な神武天皇であるという説もある。日本には徐福のお墓、徐福宮、徐福岩、徐福上陸記念碑などの遺跡がまだ残っている。1991年に、日本の佐賀県には「徐福ロード」という公園が建てられた。現在も、毎年秋には佐賀県の人々が徐福に「初穂」をささげ、50年ごとに盛大な式典を行っている。
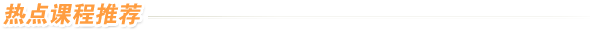 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|